🏫 地域が“学びのキャンパス”に
2025年5月25日朝、文部科学省は「地域まるごと学び場構想」を2026年度から全国展開する方針を明らかにしました。この制度は、少子化による小中学校の統廃合が進む中、“地域全体を教育資源と捉えた新しい学び方”を制度化するものです。
例えば、地域の図書館、公民館、農園、工場、美術館、商店などを“分散型学び拠点”とし、教室外でも単位取得や評価が可能になる仕組みが導入されます。
🧭 制度の概要と背景
– 対象:全国の小中学校および市町村教育委員会
– 目的:
– 少子化で縮小する学校空間の代替機能を確保
– 子どもの多様な学びニーズに応える
– 地域資源を活かした“実社会接続型教育”を強化
– モデル地域:新潟県十日町市、島根県雲南市、岡山県真庭市などで先行実施
特に「地域の担い手育成」「過疎地域の教育格差解消」を意識した政策設計となっています。
📚 具体的な“学びの拠点”事例
– 地元の商店街でキャッシュレス体験授業
– 農業体験を通じた“理科+社会”融合授業
– [[PRODUCT:子ども用タブレット 地域学習アプリ対応モデル]] を活用した現地解説付きウォーキングラリー
– 高齢者と共同での“地域史聞き書き”プロジェクト
こうした活動も教員や教育委員会の評価により「学校の成績」として反映可能になります。
🧠 現場・保護者・専門家の声
– 教員:「“教室で完結しない学び”がようやく制度化される」
– 保護者:「うちの子は座学が苦手なのでありがたい」
– 教育社会学者:「コミュニティの一体感醸成にも資する取り組み」
特に、不登校や学習意欲の低下が見られる子どもへのアプローチとしても注目されています。
👓 筆者の考察:学びの“実感”が教育の核心になる
私は大学時代に教育実習で地方の中山間地域を訪れた経験があります。そこで感じたのは、「子どもたちは街の空気に敏感に反応し、教科書以上に地域から学んでいる」という事実です。
この制度がうまく機能すれば、“教えること”と“育つこと”が教室外でも自然に結びつき、教育のあり方が変わるはずです。
また、地元の人たちが“子どもの学びの相手役”になることで、地域と学校が共に生きる新しい風景が見えてくるのではないでしょうか。
📅 今後のスケジュールと展望
– 2025年夏:パイロット地域の公募・選定開始
– 2026年4月:制度開始、100地域で先行実施
– 2027年以降:全国の1,000地域で導入予定
– 教員研修プログラムや“地域教育コーディネーター”育成事業も並行実施へ
文科省はまた、家庭や民間事業者も巻き込んだ“複合型学習”の未来像を描きつつ、制度の持続可能性を確保する方向で準備を進めています。
📌 まとめ:“まち”が“まなび”に変わる未来へ
地域まるごと学び場構想は、少子化や教育格差といった複雑な社会課題を、「地域」と「子ども」が協力して乗り越えていく新たなビジョンです。
学校という枠を超えた“地域総出の教育”によって、学びの形がもっと自由に、もっと意味あるものになっていく──そんな時代が、すぐそこまで来ています。

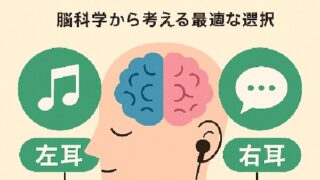
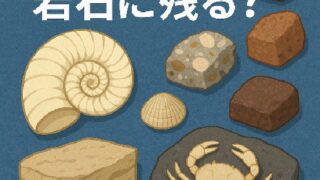
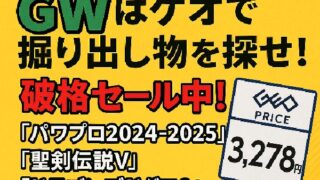





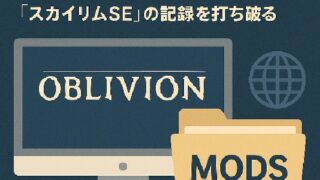
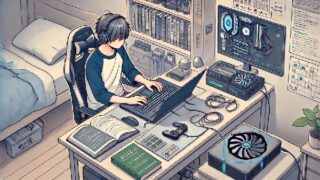
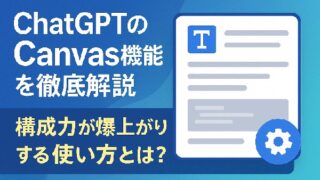

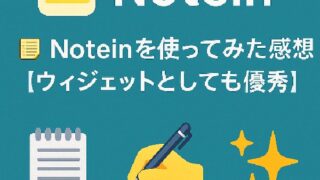

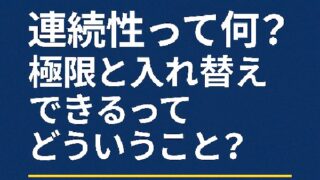

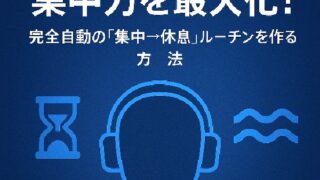



コメント