🏥 地方医療機関にも“医師の働き方改革”が本格化
2025年5月25日夜、厚生労働省は全国の地方病院に向けて「医師の勤務時間適正化ガイドライン(第2版)」を公開し、地域偏在を抱える医療機関での長時間勤務是正を強化する方針を発表しました。
特に救急医療や産科・小児科などの“24時間体制”が必要な診療科で、勤務医の過重労働が常態化していることが指摘されており、2024年の制度開始から1年を経て、地方展開の必要性が明確になったかたちです。
🔄 改革の中核となる取り組み
– 医師の勤務時間管理義務化(最大年1860時間)
– 地域医療連携による“交代制チーム”の構築
– AIによる診療補助・問診サポートの導入(例:
医師の働き方改革完全解説/益原大亮【3000円以上送料無料】
💰 4,840円
🛍️ 楽天で見る
)
– 救急外来の“夜間応援体制”の地域間連携
また、地域医師会や大学病院との「人材プール化」も進められ、繁忙期における応援医派遣のマッチングがデジタル化されつつあります。
📊 なぜ“地方”に焦点が当たるのか?
– 地方病院の6割以上が「夜間1人医体制」で運営(2024年厚労省調査)
– 医師の高齢化・専門科の偏在(産婦人科、小児科、外科で特に顕著)
– 若手医師の都市集中化による“診療空白”の発生
このままでは「医療機能の縮小」や「救急断り」が連鎖する恐れがあり、“持続可能な体制”の構築が急務とされています。
🧠 医療現場と自治体の声
– 北陸地方の病院長:「AI問診は医師の初期負担を軽減し、診察の質も安定」
– 中部の自治体職員:「隣町との連携で当直体制が交互に組めるようになった」
– 若手医師:「勤務時間が明確化され、将来の働き方設計がしやすくなった」
一方で、「AIの判断に依存しすぎる懸念」や「緊急対応に必要な判断力の継承」が課題とされ、人的教育との両立が求められます。
✍ 筆者の考察:テクノロジーと“持続可能な医療”の両立
私は以前、地方の診療所でボランティアとして働いた経験があります。そこでは、夜間救急を1人で何日も担当する医師の姿が当たり前で、過労や判断ミスが深刻なリスクとなっていました。
今回の改革は、単なる“休みを増やす”政策ではなく、「患者と向き合う時間」を守るための制度だと感じます。
技術によって“人を減らす”のではなく、“人が本来の役割に集中できる”環境を整える──その発想が地域医療の未来を支える鍵となるのではないでしょうか。
📆 今後のスケジュールと期待
– 2025年秋:AI問診システムの導入補助制度(全国100病院対象)
– 2026年:地域医療連携プラットフォームの全国展開
– 2027年:医師偏在是正に向けた新たな奨学金制度導入
政府はまた、勤務実態の“見える化”を進めるとともに、医療機関ごとの導入状況の公開によって、透明性と市民の理解促進を図る構えです。
📌 まとめ:“医療を支える人”を支える制度へ
医師の働き方改革は、単なる労働条件の見直しにとどまらず、「いかにして医療を続けるか」という社会全体の問いでもあります。
地域の命を守るために、現場に寄り添い、技術と連携した柔軟な制度設計が今こそ求められています。
医師の働き方改革完全解説/益原大亮【3000円以上送料無料】
💰 4,840円
🛍️ 楽天で見る
【中古】地方の病院は「医師の働き方改革」で勝ち抜ける
💰 7,238円
🛍️ 楽天で見る
脳神経外科速報 2022年6号(第32巻6号)特集:「医師の働き方改革」と脳神経外科医の取り組み
💰 1,489円
🛍️ 楽天で見る

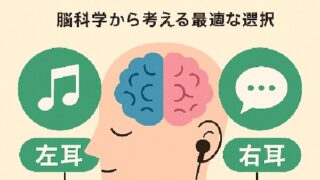
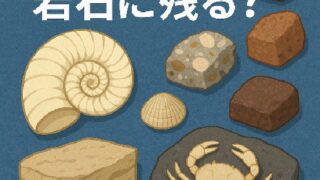
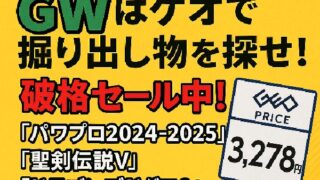





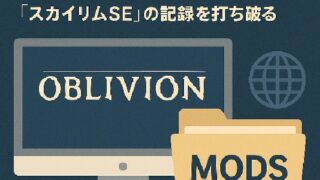
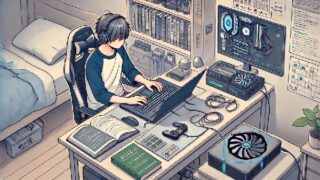
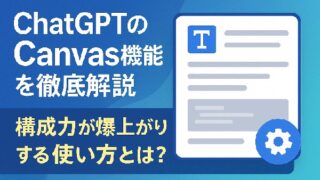

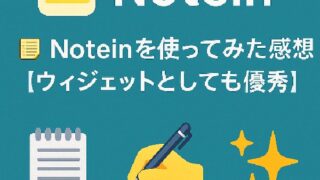

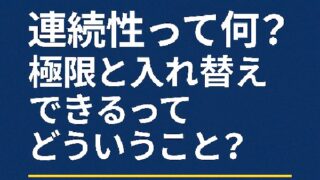

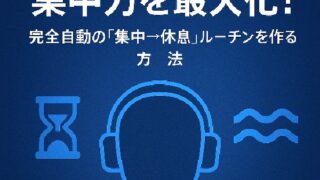
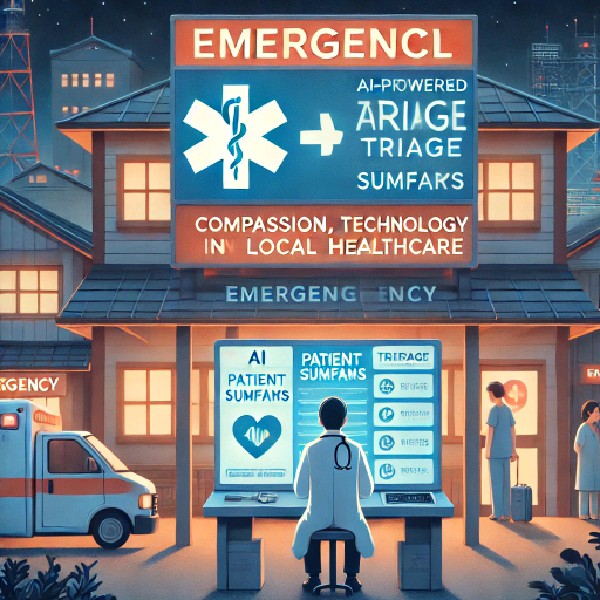


コメント