はじめに
ChatGPTの進化に伴い、文章やアイデアの整理・編集・発信がますます効率化しています。その中でも特に注目されているのが「Canvas(キャンバス)」という新機能です。
このCanvasは、従来の対話形式を補完し、長文の編集・構成を視覚的に管理するための新しいインターフェースとして登場しました。この記事では、Canvasの基本から活用方法、実践テクニック、将来的な可能性まで徹底的に解説します。
Canvasとは?
Canvasとは、ChatGPT内で使えるビジュアル型のテキスト編集機能です。ユーザーが作成したコンテンツを構造化し、セクションごとに表示・編集したり、AIから提案をもらいながら構成を練ったりできるのが特徴です。
簡単に言えば、「Wordのアウトラインモード」+「リアルタイムAI提案」+「Markdownエディタ」が融合したような体験が可能になります。
主な特徴とできること
1. セクション単位での編集
Canvasは文書全体を「セクション」単位で分け、見出しや段落ごとに管理できます。たとえば、タイトル・導入・本文・結論…という構成をブロック化して、個別に編集・入れ替えが可能。
2. AIによる構成提案とフィードバック
各セクションに対して、ChatGPTが「続きの文章」「言い換え」「要約」「補足説明」を提案してくれます。構成の漏れや重複も検知して教えてくれるため、自然と完成度が高まります。
3. 下書きと清書の分離
構成中のアイデアと、完成に近い文書を別々に扱えるため、ドラフト作成から清書までの流れがスムーズ。途中で方向転換しても迷子にならずに済みます。
4. マークダウン出力対応
完成した記事はMarkdown形式で書き出し可能。ブログやCMSへの転用も簡単です。
Canvasを活用するメリット
視覚的に構成を確認できる
アイデアが散らからず、論理の飛躍や重複を防ぐことができます。特に、複雑な議論や技術記事など、複数の段階を経る文章には最適です。
長文も怖くない
従来、AIとの対話で長文を作る場合、内容が途中でズレたり、修正が大変だったりしました。Canvasを使えば、セクションごとに調整しながら組み立てられるので安心です。
チームでの共有がしやすい(今後対応予定)
OpenAIは将来的に、Canvasのチーム共有やコラボ編集機能を追加する予定とされています。複数人で構成を考える作業にも有効です。
どんな時に使うと便利?
– ブログ記事の執筆・構成チェック
– プレゼン資料や企画書の下書き
– エッセイやレポートの全体像把握
– AIに任せつつ文章を育てたい時
Canvasの操作感(簡易レビュー)
– ブロックの移動がスムーズ:ドラッグ&ドロップで構成の入れ替えができる
– AI提案の反映もワンクリック:推敲や言い換えがボタン一つ
– シンプルな見た目で集中しやすい:見た目がごちゃつかず、構成だけに集中できる
今後期待されるアップデート
– リアルタイム共同編集(Google Docs的な機能)
– コメント機能(チーム間でフィードバック)
– タグ・カテゴリ管理(記事分類や検索用)
– Webページ構成に合わせたテンプレート対応
まとめ
ChatGPTのCanvas機能は、AIと文章を書くすべての人にとって「構成力を補強する最強の味方」です。従来の一方通行の生成では難しかった、“練る・整える・伝える”という過程を、驚くほど滑らかにしてくれます。
これからの執筆は、ただの執筆ではありません。AIと共に「設計しながら書く」──それを可能にするのが、Canvasという新しいステージなのです。
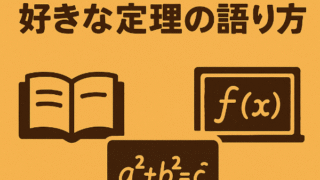





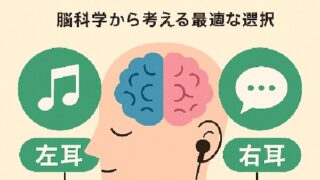
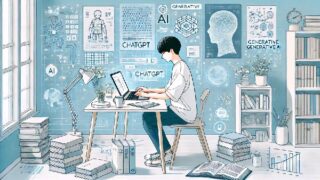


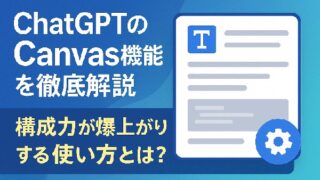

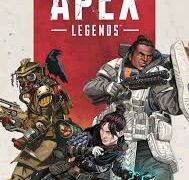
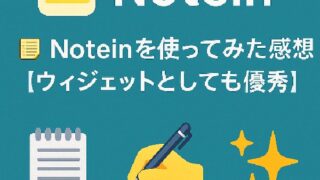

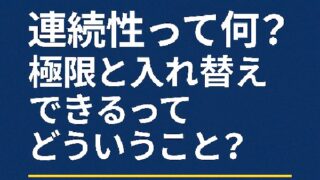

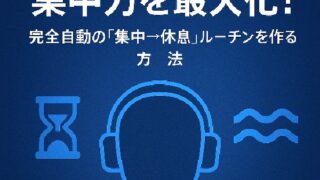
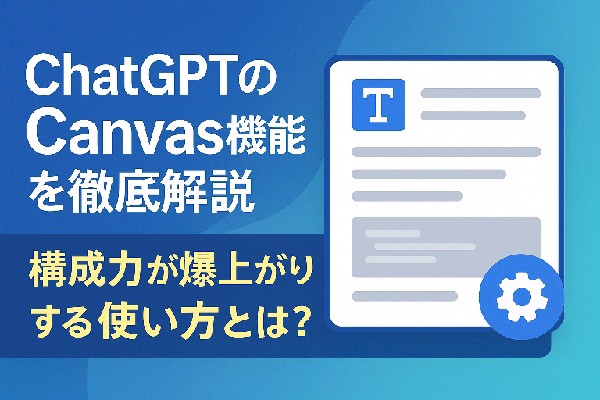
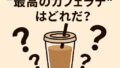

コメント